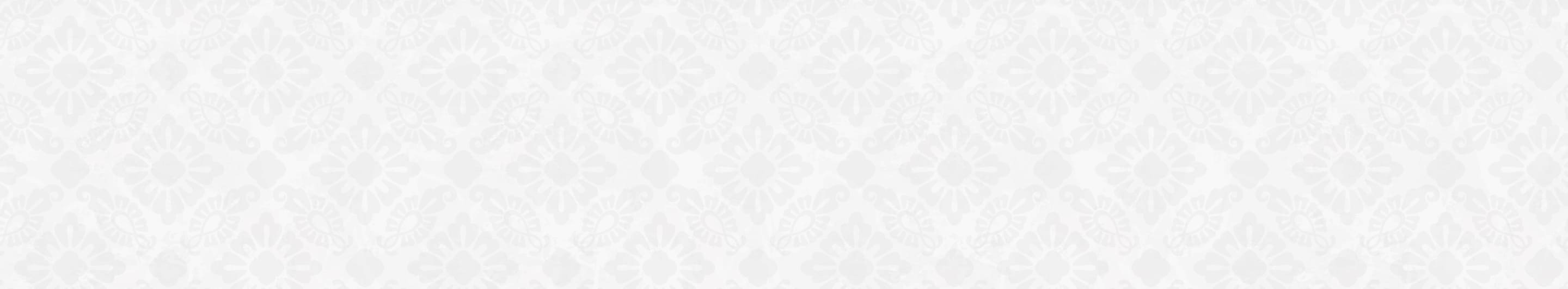
天社宮由緒

天社宮 由緒
社号
第百十二代・霊元天皇の御代、天和二年(1682年)の佳日に、畏れ多くも勅宣を拝し、「天社宮」の尊称を賜りました。
社格
延喜式の古い記録には、各神社に勅許による神階が定められた由緒が詳しく示されております。特に、若狭の加茂神社に伝わる土御門家所蔵「谷川文書」のうち、「天神地祇」と題された古書には、延喜式に記された六十余州の三社ならびに、その他の神々の位階が記されております。
その一節に、
第一 天照皇大神宮
第二 春日大明神
第三 天社宮泰山府君
と記され、これに続き、大日本国六十余州の一宮が列挙され、さらに五畿内五カ国の神社として、
山城国 加茂大明神
大和国 三輪大明神
河内国 平岡大明神
和泉国 大鳥大明神
摂津国 住吉大明神
と記されております。
天社宮 由緒
天社宮の悠久なる歴史は、誠に由緒深いものでございます。
今から千三百年前の養老元年(717年)、遣唐使として唐に渡った阿倍仲麻呂公は、中国の難関「科挙」に合格し、玄宗皇帝にお仕えしておりました。仲麻呂公が大変優秀であられたことから、皇帝より深い御寵愛を賜り、その御恩寵により、中国の最も尊き霊山、泰山より大元尊神(太一)の御神霊の宿る御宝体を賜ったのでございます。
かくも尊き御神体と、仲麻呂公が修得された多くの秘法を、天皇家、安倍家へ伝えるべく、同じく遣唐使であった、賀茂家の祖、吉備真備公に託されたのでございます。
吉備真備公が帰国された翌年の天平八年(736年)十二月十三日、聖武天皇は、平城京の北方位にあたる若狭国名田庄を泰山府君祭料知行地とお定めになりました。これは、北斗七星(太一)のある北の方位が最も尊い方位とされるためでございます。(なお、現在も続く若狭から東大寺への「お水送り」の神事も、北方位の聖なる水を都へ送るという、この地の神聖性を今に伝える行事でございます。)
さて、吉備真備公より御神体を託された賀茂家は、以後代々にわたって大切にお守りし続けました。そして時を経て、阿倍仲麻呂公との約束どおり、安倍晴明公の父・安倍保名へと伝えられたのでございます。こうして尊き御神体は、ついに安倍家(土御門家)において大切にお祀りされることとなったのでございます。
平安時代には、京都の堀川一条葭屋町にある大陰陽師・安倍晴明公の邸内にお祀りされておりましたが、応仁の乱により社殿が焼失してしまいました。しかしながら、幸いにも御神体は難を逃れ、無事に泰山府君祭料知行地である若狭名田庄へと遷されたのでございます。
やがて長享二年(1488年)になりますと、安倍家の後継である土御門有宣卿が、若狭名田庄において社殿を再興されました。この地は、すでに正和六年(1317年)に花園天皇より土御門家による泰山府君大神(太一)の祭料地と定められた由緒ある聖地でございました。土御門有宣卿はここに居城を構え、厳粛なる遷宮の儀を執り行われたのでございます。以後百余年にわたり、若狭名田庄は陰陽寮による国家祭祀が行われる太一信仰の聖地として、深い崇敬を集めることとなりました。
時代は下って慶長五年(1600年)、安倍久脩卿が勅命により若狭から京都へお戻りになり、下京区七条下ル唐橋の地に社殿を建立されました。そして翌年、徳川家康公より土御門家は陰陽道宗家に任じられたのでございます。これ以降、歴代天皇と将軍の御即位に際しては、土御門家によって天に帝の即位をお伝えする「天胄地府祭」が斎行されることとなりました。実に御陽成天皇より孝明天皇に至る十四代の天皇、また徳川家康公より家茂公に及ぶ十四代の将軍の大祭が、天社宮にて執り行われたのでございます。
太一の神を唯一お祀りする天社宮は、その特別な地位ゆえに、二十年ごとの御内侍所賢所の御造営替えの折には、幾度も土御門家へ仮殿が下賜されるという光栄に浴しました。
しかしながら、明治維新による陰陽道禁止令と廃仏毀釈により、天社宮は取り壊され、土御門家は京都の天文台や邸宅をすべて失うこととなってしまいました。それでもなお、第二次世界大戦終結の翌年まで七十八年の長きにわたり、代々の土御門家によって太一の御神体は篤くお祀りされ続けたのでございます。そして陰陽道の思想(太一信仰)もまた、日本の節句等の年中行事や伝統文化、暦、神事作法として残り続けたのでございます。
やがて復興の機運が訪れます。昭和十七年(1942年)、「土御門神道同門会」が結成され、土御門子爵家当主・土御門熙光が総裁、分家筋の倉橋泰隆が会長となり、土御門神道復興の動きが始まりました。伊勢神宮大宮司を出された三室戸家の御後援を賜り復興を進めておりましたが、昭和十九年に熙光が薨去され、弟君の範忠が跡を継がれることとなりました。
そして昭和二十一年(1946年)五月二十一日、ついに「天社土御門神道」として再興される運びとなったのでございます。同年、若狭名田庄より土御門家の親族でもあり、代々土御門家にお仕えしてきた藤田家三十七代目・藤田乾堂が上京し、同族や同門の人々と協力して天社宮の再興に尽力されました。
昭和二十九年(1954年)一月十一日には、「宗教法人天社土御門神道本庁」として文部大臣の認証を拝受し、本部たる「天社土御門神道本庁」を設置いたしました。管長に土御門範忠、代表兼庁長に藤田乾堂が就任し、太一の御神体を受け継ぐ体制がここに整えられたのでございます。


 かくして、終戦直後の苦難の時代にあっても、土御門家ならびに多くの同門の方々の篤い御尽力により、御神体は一旦京都へ仮安置された後、太一の聖地である若狭名田庄へと改めて遷宮されました。そして現在に至るまで、この地において尊い信仰が大切に守り伝えられているのでございます。
かくして、終戦直後の苦難の時代にあっても、土御門家ならびに多くの同門の方々の篤い御尽力により、御神体は一旦京都へ仮安置された後、太一の聖地である若狭名田庄へと改めて遷宮されました。そして現在に至るまで、この地において尊い信仰が大切に守り伝えられているのでございます。
