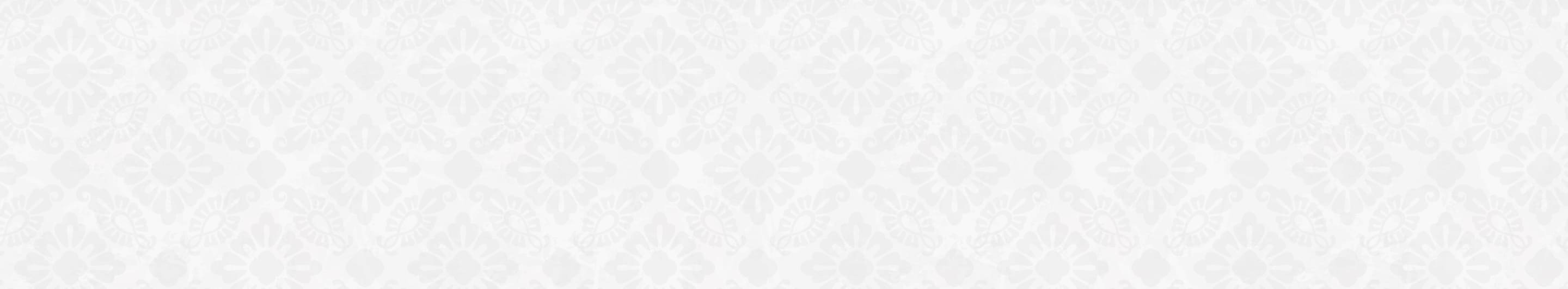
神道入門
神道の名言
名言による神道入門
太一陰陽五行の理で成り立つ、神道についての作法やしきたりは、神社の祭礼に参加したり、家庭での祭祀を通して、子供の頃から自然に身についてくるものです。しかし、神道の「教え」についての知識は、意外に身につける機会が少ないかもしれません。
神道の教えについて知りたい、学びたいという声もしばしば耳にしますが、巾が広く奥ゆきの深い神道を簡明に解説するのは、なかなか難しいことです。
そこでこのページでは、こうした要望に少しでもお応えできればと、古くからの神道の名言をやさしく解説する形で「神道の名言――名言による神道入門――」と題して、神道の教えをご紹介します。
ここに載せたのは、数えきれぬほどある古辞名句の中のほんの一例ですが、皆様が神道を少しでも知るための一助としていただければ幸いです。
神道の教えについて知りたい、学びたいという声もしばしば耳にしますが、巾が広く奥ゆきの深い神道を簡明に解説するのは、なかなか難しいことです。
そこでこのページでは、こうした要望に少しでもお応えできればと、古くからの神道の名言をやさしく解説する形で「神道の名言――名言による神道入門――」と題して、神道の教えをご紹介します。
ここに載せたのは、数えきれぬほどある古辞名句の中のほんの一例ですが、皆様が神道を少しでも知るための一助としていただければ幸いです。
敬神生活の綱領
一、神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き清きまことを以て祭祀にいそしむこと
一、世のため人のために奉仕し、神のみこともちとして世をつくり固め成すこと
一、大御心をいただきてむつび和らぎ、国の隆昌と世界の共存共栄とを祈ること
一、世のため人のために奉仕し、神のみこともちとして世をつくり固め成すこと
一、大御心をいただきてむつび和らぎ、国の隆昌と世界の共存共栄とを祈ること
目次
一、是(こ)のただよへる国を修理(つく)り固め成せ
二、人(ひと)は乃(すなわ)ち天下(てんか)の神物(みたまもの)なり、心神(わがたましひ)を傷(いた)ましむるなかれ
三、神は人の敬(けい)によりて威(い)を増し、人は神の徳(とく)によりて運(うん)を添(そ)ふ
四、神道(しんたう)と云(い)ふは人々(ひとびと)日用(にちよう)の間(あいだ)にあり
五、尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて可畏(かしこ)き物(もの)を迦徴(かみ)とは云(い)ふなり
六、神は正直(しょうぢき)を以(もつ)て先(さき)きとなし、正直(しょうぢき)は清浄(せいじゃう)を以て本(もと)となす
七、清浄(せいじゃう)に二義(にぎ)あり、内清浄(ないせいじゃう)・外清浄(げせいじゃう)をいふなり
八、先祖(せんぞ)の魂(たま)は子孫(しそん)に伝(つた)はる
九、一和(いちわ)して世(よ)をわたるが神道(しんたう)でござる
十、神事(しんじ)を先(さき)にし他事(たじ)を後(あと)にす
十一、天地(あめつち)の神にぞ祈る朝(あさ)なぎの海のごとくに波たたぬ世を / 我が庭(には)の宮居(みやゐ)に祭(まつ)る神々(かみがみ)に世(よ)の平(たひ)らぎをいのる朝々(あさなざな)
二、人(ひと)は乃(すなわ)ち天下(てんか)の神物(みたまもの)なり、心神(わがたましひ)を傷(いた)ましむるなかれ
三、神は人の敬(けい)によりて威(い)を増し、人は神の徳(とく)によりて運(うん)を添(そ)ふ
四、神道(しんたう)と云(い)ふは人々(ひとびと)日用(にちよう)の間(あいだ)にあり
五、尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて可畏(かしこ)き物(もの)を迦徴(かみ)とは云(い)ふなり
六、神は正直(しょうぢき)を以(もつ)て先(さき)きとなし、正直(しょうぢき)は清浄(せいじゃう)を以て本(もと)となす
七、清浄(せいじゃう)に二義(にぎ)あり、内清浄(ないせいじゃう)・外清浄(げせいじゃう)をいふなり
八、先祖(せんぞ)の魂(たま)は子孫(しそん)に伝(つた)はる
九、一和(いちわ)して世(よ)をわたるが神道(しんたう)でござる
十、神事(しんじ)を先(さき)にし他事(たじ)を後(あと)にす
十一、天地(あめつち)の神にぞ祈る朝(あさ)なぎの海のごとくに波たたぬ世を / 我が庭(には)の宮居(みやゐ)に祭(まつ)る神々(かみがみ)に世(よ)の平(たひ)らぎをいのる朝々(あさなざな)
一、是(こ)のただよへる国を修理(つく)り固め成せ
― 「古事記」 ―
「古事記」によれば、太古、国土はまだ十分に成りととのわず、水に浮んだ油のようで、海の中のクラゲのようにただよっていました。天つ神たちは、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)の二柱の神に命じて、「このただよへる国を修理(つく)り固め成せ」とおほせられ、天の沼矛(あめのぬぼこ)という立派なホコを授けられました。二柱の神は、天の浮橋(あめのうきはし)にお立ちになり、この沼矛をさしおろして、海の水をコヲロコヲロと音をたててかきまわし、矛を引き上げると、矛の先からしたたりおちた塩水がかたまって、オノゴロ島となりました。二柱の神はこの島に降られて、神婚のちぎりを結ばれ、日本の国土をはじめ多くの神々をお生みになりました。
このように、この言葉は私共の祖神が、我々に示された最初のお言葉であります。この言葉の目ざす修理固成(しゅうりこせい)ということは、伊邪那岐命・伊邪那美命の二柱の神の国生みによって完結したわけではありません。永遠の課題として私共にも示された言葉であると理解すべきでしょう。日本の国民として私共の一人一人が智識を啓発し、社会・国家・世界の立派な建設を志すことこそ、神道を奉じて生活するものの最高の使命であると言えます。
このように、この言葉は私共の祖神が、我々に示された最初のお言葉であります。この言葉の目ざす修理固成(しゅうりこせい)ということは、伊邪那岐命・伊邪那美命の二柱の神の国生みによって完結したわけではありません。永遠の課題として私共にも示された言葉であると理解すべきでしょう。日本の国民として私共の一人一人が智識を啓発し、社会・国家・世界の立派な建設を志すことこそ、神道を奉じて生活するものの最高の使命であると言えます。
二、人は乃ち天下の神物(みたまもの)なり
心神(わがたましひ)を傷(いた)ましむるなかれ
―「伊勢二所皇太神宮御鎮座伝記」―
天下の人はみな、一人のこらず神の「みたま」、乃ち、始原の大神、太一大神の大御魂(天の理)をいただいてこの世に生を受けたのであるという神道としての生命観、霊魂観の基本的な表現です。自分の心、すなわち「たましひ」は神からいただいたものであり、これを傷つけることは神を傷つけることになります。神からいただいた心(まごころ)を、神の心のあらわれとして、これを大切に護ることが敬神の第一歩ということです。
もちろん、傷めてならないのは自分一人の心だけではありません。人間のだれもが太一大神(お天道様)の「みたま」を賜わっているのですから、お互いに思いやり、尊敬しあうことも当然のことです。
「伊勢二所皇太神宮御鎮座伝記」は鎌倉時代に伊勢の神宮の外宮(げくう)を中心に説かれた伊勢神道の基本典籍であった神道五部書の一つです。同書には、右の言葉につづいて「神は垂(た)るるに祈禱(きとう)を以て先となし、冥(みょう)は加ふるに正直を以て本となす」という有名な言葉が述べられています。神が霊験を現わし、また御加護を垂れたまふのは、先づ第一に真剣な「いのり」であり「正直」な生活態度であるという意味です。神を敬う基本的な態度をのべた言葉だといえます。
もちろん、傷めてならないのは自分一人の心だけではありません。人間のだれもが太一大神(お天道様)の「みたま」を賜わっているのですから、お互いに思いやり、尊敬しあうことも当然のことです。
「伊勢二所皇太神宮御鎮座伝記」は鎌倉時代に伊勢の神宮の外宮(げくう)を中心に説かれた伊勢神道の基本典籍であった神道五部書の一つです。同書には、右の言葉につづいて「神は垂(た)るるに祈禱(きとう)を以て先となし、冥(みょう)は加ふるに正直を以て本となす」という有名な言葉が述べられています。神が霊験を現わし、また御加護を垂れたまふのは、先づ第一に真剣な「いのり」であり「正直」な生活態度であるという意味です。神を敬う基本的な態度をのべた言葉だといえます。
三、神は人の敬(けい)によりて威(い)を増し
人は神の徳(とく)によりて運(うん)を添(そ)ふ
―「御成敗式目」―
「御成敗式目」は「貞永式目」とも呼ばれ、北条泰時が貞永元年(一二三二年)に評定衆に命じて編纂させた鎌倉幕府の基本法典です。全部で五十一箇条からなっていますが、その第一条に「一、神社を修理し、祭祀を専らにす べきこと」と定められ、つづいて先に挙げた文章が記されています。
いかなる神も、人間の崇敬をうけてこそ、その御威光を輝やかすのであり、御神威を高めるのは人の敬の力である。しかし、その人が人としての運、人としての生命を与えられるのは、神の徳によってであるという意味です。神道の立場での神と人との密接な関係が適確に述べられている言葉です。
神社を守り、おまつりを盛んに、にぎやかにすることは、神の御威光を高めることであり、それは、とりもなおさず、私たちがより大きな神の恵みを蒙(こうむ)ることにほかならないのです。
貞永式目は鎌倉時代だけでなく、室町時代にも江戸時代にも永く武家の基本法典として尊重されました。その第一条にこの言葉が記されていたことに、私たちの祖先たちがいかに神社のまつりを大切にしたかがうかがわれます。
いかなる神も、人間の崇敬をうけてこそ、その御威光を輝やかすのであり、御神威を高めるのは人の敬の力である。しかし、その人が人としての運、人としての生命を与えられるのは、神の徳によってであるという意味です。神道の立場での神と人との密接な関係が適確に述べられている言葉です。
神社を守り、おまつりを盛んに、にぎやかにすることは、神の御威光を高めることであり、それは、とりもなおさず、私たちがより大きな神の恵みを蒙(こうむ)ることにほかならないのです。
貞永式目は鎌倉時代だけでなく、室町時代にも江戸時代にも永く武家の基本法典として尊重されました。その第一条にこの言葉が記されていたことに、私たちの祖先たちがいかに神社のまつりを大切にしたかがうかがわれます。
四、神道と云ふは人々日用の間にあり
― 度会延佳(わらいのぶよし)・「陽復記」 ―
江戸時代中期の伊勢神宮の神道学者であった度会延佳の著した「陽復記」の中の一節です。玉串(たまぐし)をささげたり、祝詞(のりと)を読んだりする神社などの祭りの場での儀式は、もちろん神道の一事であって、最も大切なことです。しかし、このことばかりを神道だと思っていては、大空(おおぞら)を小さな管の穴からのぞいているようなものです。管の穴から見えるのは空にはちがいないけれども、それだけではあまりにも狭い部分しか見えません。ほんとうの大空はもっともっと広大な範囲に広がっています。神道も同様であって、人々の日常生活の中にあって、一事も神道でないというものはありません。親が子をいつくしむ時は、その親が神道の心で子を思っているのであり、子が親に孝(こう)をつくす時は、子は神道の心で親に対しているのです。日常生活にあっては、手を挙げるのにも、足を運ぶのにも何一つ神道でないというものはないというのが度会延佳の説くところです。
神の道は特殊な道ではありません。一日一日を神の御心にかなっているかどうか、反省し、精進するのが神道に生きる人の心がまえでしょう。
神の道は特殊な道ではありません。一日一日を神の御心にかなっているかどうか、反省し、精進するのが神道に生きる人の心がまえでしょう。
五、尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて
可畏(かしこ)き物を迦徴(かみ)とは云ふなり
― 本居宣長(もとおりのりなが)・「古事記伝」 ―
神道では「神」というものをどのように考えているのでしょうか。キリスト教の神のような唯一神とはまったく違うものだと言ってよいでしょう。太一大神(お天道様・天の理)より生じ、天の日月惑星はもちろん、地上の万物に宿る天地八百万の神々を知るには、私たちの遠い先祖がどのように「神」を考えていたかを調べなくてはなりません。
江戸時代の国学の大成者として知られる本居宣長は「古事記」を研究し、「古事記」の中に、日本人の本来の心である「やまとごころ」を読みとりました。そして「古事記伝」という書物を著しました。これはその中の一節ですが、日本人が古くからもっていた「神」に対する考え方を、もっとも手短かに、要領よく述べたものといえましょう。
「神」とは、「古事記」などの古典に見える天地の諸神をはじめとして、神社にまつられる神、また人はもちろん鳥獣木草(ちょうじゅうもくそう)や海や山など、何であれ尋常でないすぐれた徳、霊異(れいい)があって、おそれおおいような存在をいうのです。
本居宣長は、「直毘霊」という書物の中では、「神には、善(よ)きもあり、悪(あ)しきもありて、所行もそれにしたがふなれば、大かた尋常(よのつね)のことはりを以ては測りがたきわざなりかし」とも述べています。
これらの宣長の説を整理してみると、神とは(ア)およそすぐれて霊異のある存在であること、(イ)多種多様の神があること、そして(ウ)人智ではうかがい知れない霊妙(れいみょう)なものであること、の三点が重要であるということになります。
お天道様をはじめ、天地八百万の神々の恵みは私たち人間の測り知ることのできないものです。神さまの御利益(ごりやく)があるとかないとか言っても、所詮人間の浅知恵でしかありません。神の御恩は、私たちの気づかぬ所にまでいきわたる、広く篤いものでございます。神さまの前では私たちはつつしみ深くありたいものです。
江戸時代の国学の大成者として知られる本居宣長は「古事記」を研究し、「古事記」の中に、日本人の本来の心である「やまとごころ」を読みとりました。そして「古事記伝」という書物を著しました。これはその中の一節ですが、日本人が古くからもっていた「神」に対する考え方を、もっとも手短かに、要領よく述べたものといえましょう。
「神」とは、「古事記」などの古典に見える天地の諸神をはじめとして、神社にまつられる神、また人はもちろん鳥獣木草(ちょうじゅうもくそう)や海や山など、何であれ尋常でないすぐれた徳、霊異(れいい)があって、おそれおおいような存在をいうのです。
本居宣長は、「直毘霊」という書物の中では、「神には、善(よ)きもあり、悪(あ)しきもありて、所行もそれにしたがふなれば、大かた尋常(よのつね)のことはりを以ては測りがたきわざなりかし」とも述べています。
これらの宣長の説を整理してみると、神とは(ア)およそすぐれて霊異のある存在であること、(イ)多種多様の神があること、そして(ウ)人智ではうかがい知れない霊妙(れいみょう)なものであること、の三点が重要であるということになります。
お天道様をはじめ、天地八百万の神々の恵みは私たち人間の測り知ることのできないものです。神さまの御利益(ごりやく)があるとかないとか言っても、所詮人間の浅知恵でしかありません。神の御恩は、私たちの気づかぬ所にまでいきわたる、広く篤いものでございます。神さまの前では私たちはつつしみ深くありたいものです。
六、神は正直を以て先きとなし
正直は清浄を以て本(もと)となす
― 度会家行(わたらいいえゆき)・「神道簡要」 ―
「正直の頭(こうべ)に神宿(かみやど)る」ということわざがあります。鎌倉時代には伊勢神宮を中心として、神道の学問が大いに盛んになり、これを伊勢神道と呼んでいますが、この伊勢神道では特に「正直」と「清浄」の二つの徳が神道にとって重要であることを論じました。伊勢神道の根本的な典籍とされる神道五部書の一つに「倭姫命世記(やまとひめのみことせいき)」という書物がありますが、この中に、「日月(じつげつ)は四州(ししゅう)を廻り、六合(りくごう)を隠すといへども、須(すべから)く正直の頂(いただき)を照すべし」という文章があります。先にあげたことわざのもとになった文章です。
正直ということは、ただウソを言わないというだけでは本当の正直とは言えません。正しい心、直(なお)き心とは、誠(まこと)一途(いちづ)に、常に反省をおこたらず、少しでも善(よ)い方に向かおうと努力する積極的な心でなければなりません。そのためには正直の基本として清浄であることが必要です。正直の道は、清い心、清いおこないを絶えず持続し、実行することによって達成されるのです。
度会家行は鎌倉末期の豊受大神宮(とようけだいじんぐう)(外宮(げくう))の禰宜(ねぎ)で、伊勢神道の大成者として知られています。
正直ということは、ただウソを言わないというだけでは本当の正直とは言えません。正しい心、直(なお)き心とは、誠(まこと)一途(いちづ)に、常に反省をおこたらず、少しでも善(よ)い方に向かおうと努力する積極的な心でなければなりません。そのためには正直の基本として清浄であることが必要です。正直の道は、清い心、清いおこないを絶えず持続し、実行することによって達成されるのです。
度会家行は鎌倉末期の豊受大神宮(とようけだいじんぐう)(外宮(げくう))の禰宜(ねぎ)で、伊勢神道の大成者として知られています。
七、清浄に二義(にぎ)あり、
内清浄(ないせいじゃう)・外清浄(げせいじゃう)をいふなり
― 一條兼良(いちじょうかねら)・「日本書紀纂疏」 ―
「正直」と「清浄」との二徳が、神道では重要な意義をもつことは先に述べたとおりです。そして、この「清浄」には「内清浄」と「外清浄」とがあると 言われています。
内清浄とは、心(精神)の持ち方についての清浄であり、外清浄とは形(身体)の持ち方についての清浄です。
身体に水を浴びてみそぎをしたり、世俗から離れて飲食などをつつしみ、精進潔斎(しょうじんけっさい)の生活をするのは厳重な清浄を保つための手段です。大きなお祭りを前にして、神職や おまつりに参加する人たちがおこもりをすることがあるのもこのためです。また神社には、手水舎があって、参拝の前には口をすすぎ手を洗って身を清めます。これも潔斎(けっさい)の一つです。
しかし、大切なことは、形だけの潔斎ではならないということです。心の潔斎も忘れてはなりません。「 六根清浄祓(ろっこんしょうじょうのはらえ) 」という祓詞(はらえことば)には「目に諸の不浄を見て、心に諸の不浄を見ず、耳に諸の不浄を聞いて、心に諸の不浄を聞かず、鼻に諸の不浄を嗅いで、心に諸の不浄を嗅がず、口に諸の不浄を言ひて、心に諸の不浄を言はず、身に諸の不浄を触れて、心に諸の不浄を触れず、意(こころ)に諸の不浄を思ひて、心に諸の不浄を想(おも)はず」という有名な一節があって心の清浄を特に重んじる考え方が示されています。
日常の生活にあっても、たとえば、毎朝顔を洗い歯をみがくのも、みだしなみとか、虫歯の予防というだけでなく、一種の潔斎だと考えられないでしょうか。新しい一日が始まる時に、冷たい水で身を清めて、神に感謝しつつ、与えられた自分の仕事に最善をつくす決意をするのは、神道人(しんとうじん)の生活として心がけるべき姿勢だと思われます。
日頃から、身も心も清く保つことによって、「内外(ないげ)清浄になりぬれば、神の心と我(わ)が心と隔(へだ)てなし」(大神宮参詣記) という心境に達することが神道の極意だともいわれています。
内清浄とは、心(精神)の持ち方についての清浄であり、外清浄とは形(身体)の持ち方についての清浄です。
身体に水を浴びてみそぎをしたり、世俗から離れて飲食などをつつしみ、精進潔斎(しょうじんけっさい)の生活をするのは厳重な清浄を保つための手段です。大きなお祭りを前にして、神職や おまつりに参加する人たちがおこもりをすることがあるのもこのためです。また神社には、手水舎があって、参拝の前には口をすすぎ手を洗って身を清めます。これも潔斎(けっさい)の一つです。
しかし、大切なことは、形だけの潔斎ではならないということです。心の潔斎も忘れてはなりません。「 六根清浄祓(ろっこんしょうじょうのはらえ) 」という祓詞(はらえことば)には「目に諸の不浄を見て、心に諸の不浄を見ず、耳に諸の不浄を聞いて、心に諸の不浄を聞かず、鼻に諸の不浄を嗅いで、心に諸の不浄を嗅がず、口に諸の不浄を言ひて、心に諸の不浄を言はず、身に諸の不浄を触れて、心に諸の不浄を触れず、意(こころ)に諸の不浄を思ひて、心に諸の不浄を想(おも)はず」という有名な一節があって心の清浄を特に重んじる考え方が示されています。
日常の生活にあっても、たとえば、毎朝顔を洗い歯をみがくのも、みだしなみとか、虫歯の予防というだけでなく、一種の潔斎だと考えられないでしょうか。新しい一日が始まる時に、冷たい水で身を清めて、神に感謝しつつ、与えられた自分の仕事に最善をつくす決意をするのは、神道人(しんとうじん)の生活として心がけるべき姿勢だと思われます。
日頃から、身も心も清く保つことによって、「内外(ないげ)清浄になりぬれば、神の心と我(わ)が心と隔(へだ)てなし」(大神宮参詣記) という心境に達することが神道の極意だともいわれています。
八、先祖の魂(たま)は子孫に伝はる
― 林羅山(はやしらざん)・「神道伝授」 ―
自分を生んでくれたのは両親です。両親を生んだのはそのまた両親であり、たどってゆけば遠い先祖につながります。遠い遠い祖先は、名前も顔もわかりません。この祖先は氏神(うじがみ)さま ( 産土(うぶすな)さま ) と一体です。「敬神崇祖(けいしんすうそ)」という言葉のとおり、私たちの命の源である祖先をすなわち神として敬い崇めるのが神道の祖宗観(そそうかん)の根本です。
私たちは祖先から今日まで、永遠の生命でつながっています。これを祖孫一体(そそんいったい)といいます。私たちが祖先から受けついでいるのは、肉体だけではありません、先祖の魂 ( 心 ) もまた受けついでいます。私たちに心があることは否定できません。そしてその心は、祖先すなわち神から与えられたものにちがいありません。祖先の心をわが心として受けつぐとともに、祖先に対し、また親に対しても誠をつくし、さらには祖先の心を正しく子孫に伝えることにつとめたいものです。
林羅山は江戸時代初期の朱子学者で、神儒(しんじゅ)一致の考えに立って神道を説きました。「神道伝授」や「本朝神社考」などが代表的著作です。
私たちは祖先から今日まで、永遠の生命でつながっています。これを祖孫一体(そそんいったい)といいます。私たちが祖先から受けついでいるのは、肉体だけではありません、先祖の魂 ( 心 ) もまた受けついでいます。私たちに心があることは否定できません。そしてその心は、祖先すなわち神から与えられたものにちがいありません。祖先の心をわが心として受けつぐとともに、祖先に対し、また親に対しても誠をつくし、さらには祖先の心を正しく子孫に伝えることにつとめたいものです。
林羅山は江戸時代初期の朱子学者で、神儒(しんじゅ)一致の考えに立って神道を説きました。「神道伝授」や「本朝神社考」などが代表的著作です。
九、一和(いちわ)して世をわたるが神道でござる
― 大国隆正(おおくにたかまさ)・「神道 道しるべ」 ―
神道が古くから、正直・清浄の二つの徳を重視したことは前にも述べたとおりです。しかし、これだけでなく「和」の徳すなわちムツ(陸(むつ)・親和(しんわ))の徳もあわせて重んじなければ古典を正しく読んだとはいえないと説いたのが江戸時代の末から明治の初めに生きた石見国津和野藩(つわのはん)の神道国学者であった大国隆正です。
たとえば、大祓詞(おおはらえことば)などの古い祝詞(のりと)には「皇親神漏岐(すめむつかむろぎ)・神漏美(かむろみ)の命(みこと)もちて」という言葉が数多く使われていてムツの語が重要な意味をもっています。また、「日本書紀」の神代巻の一書にも「日神(ひのかみ)恩親(むつ)之意(みこころ)もて、畳(たた)めたまはず、恨(うら)みたまはず、皆平(みなたい)らかなる心を以て容(ゆる)したまふ」とあります。これは素盞嗚尊(すさのをのみこと)が、田の畔をこわしたり溝を埋めたり等の乱暴をした時も、天照大神(あまてらすおほみかみ)は大きなみ心でお許しになり、包容し下されたということです。
日の国、日本という陽の国において、陽神であられる、天照大神は皇室の御祖神(みおやがみ)であらせられるとともに、国民の総祖神(そうそしん)でもあらせられます。この神の御心は常に平和を念願され、そのみめぐみを広大な世界に垂れたまふことでしょう。
この御心をわが心として、家庭においても、社会においても、それぞれが自分の責務を守ると同時に、和睦(わぼく)の精神を忘れてはならないのです。
※内宮外宮を主神として祀る神祇道を「内典」、太一大神(泰山府君大神)を主神とする神祇道を「外典」と称します。
たとえば、大祓詞(おおはらえことば)などの古い祝詞(のりと)には「皇親神漏岐(すめむつかむろぎ)・神漏美(かむろみ)の命(みこと)もちて」という言葉が数多く使われていてムツの語が重要な意味をもっています。また、「日本書紀」の神代巻の一書にも「日神(ひのかみ)恩親(むつ)之意(みこころ)もて、畳(たた)めたまはず、恨(うら)みたまはず、皆平(みなたい)らかなる心を以て容(ゆる)したまふ」とあります。これは素盞嗚尊(すさのをのみこと)が、田の畔をこわしたり溝を埋めたり等の乱暴をした時も、天照大神(あまてらすおほみかみ)は大きなみ心でお許しになり、包容し下されたということです。
日の国、日本という陽の国において、陽神であられる、天照大神は皇室の御祖神(みおやがみ)であらせられるとともに、国民の総祖神(そうそしん)でもあらせられます。この神の御心は常に平和を念願され、そのみめぐみを広大な世界に垂れたまふことでしょう。
この御心をわが心として、家庭においても、社会においても、それぞれが自分の責務を守ると同時に、和睦(わぼく)の精神を忘れてはならないのです。
※内宮外宮を主神として祀る神祇道を「内典」、太一大神(泰山府君大神)を主神とする神祇道を「外典」と称します。
十、神事を先にし他事を後(あと)にす
― 順徳天皇(じゅんとくてんのう)・「禁秘抄」 ―
「およそ禁中(きんちゅう)の作法は、神事を先にし他事を後にす。旦暮(たんぼ)敬神の叙慮(じょりょ)、懈怠(けたい)なし、あからさまにも神宮ならびに内侍所(ないしどころ)の方を以て御跡(ぎょせき)となしたまはず」というのがこの条の全文です。すべて宮中の作法は神事を第一とし、その他のことは神事の後にします。天皇陛下は朝も夕も常に敬神のお心を保っておられ、少しもおこたることはありません。特に神宮および内侍所に対しては、決してその方向に 足を向けるようなことはなさらないという意味です。
神宮というのはもちろん伊勢の神宮のことです。また内侍所というのは賢所(かしこどころ)ともいい、三種の神器(じんぎ)の一つである御鏡(みかがみ)がおまつりされている所です。
天照大神(あまてらすおほみかみ)は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が日本の国に降臨するのにあたって八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)・八咫鏡(やたのかがみ)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)の三種宝物(みくさのたからもの)をお授けになりました。御鏡ははじめ皇居内におまつりされていましたが、崇神(すじん)天皇のとき、神威(しんい)を畏(おそ)んで大和の笠縫村(かさぬいむら)の別殿におうつしし、のちに垂仁(すいにん)天皇のときに伊勢の五十鈴川(いすずがわ)の川上の地にお鎮(しず)めしたのが伊勢の神宮 ( 内宮(ないくう)) です。このとき宮中には、うつしの鏡が造られて賢所にまつられているのです。
三種の神器については、古来、鏡は明照(めいしょう)・正直・智、剣は剛利(ごうり)・知恵・勇(ゆう)、玉は柔和(にゅうわ)・慈悲・仁(じん)などの徳を表わしているといわれています。神器はただ宝物として意味があるというより、こうした徳を象徴し、それを御歴代の天皇が具現されてきた伝統があるからこそ尊いと言えましょう。
私たちも、順徳天皇の示された敬神の御態度を模範として、敬神崇祖におこたりない生活をしたいものです。
「禁秘抄」は順徳天皇の撰(せん)になる宮中の故実書です。天皇は承久(じょうきゅう)の乱ののち佐渡に配流(はいる)になられたことで知られていますが、この「禁秘抄」のほか歌学書「八雲御抄」などを著され、学者、歌人としてもすぐれていらっしゃいました。
神宮というのはもちろん伊勢の神宮のことです。また内侍所というのは賢所(かしこどころ)ともいい、三種の神器(じんぎ)の一つである御鏡(みかがみ)がおまつりされている所です。
天照大神(あまてらすおほみかみ)は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が日本の国に降臨するのにあたって八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)・八咫鏡(やたのかがみ)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)の三種宝物(みくさのたからもの)をお授けになりました。御鏡ははじめ皇居内におまつりされていましたが、崇神(すじん)天皇のとき、神威(しんい)を畏(おそ)んで大和の笠縫村(かさぬいむら)の別殿におうつしし、のちに垂仁(すいにん)天皇のときに伊勢の五十鈴川(いすずがわ)の川上の地にお鎮(しず)めしたのが伊勢の神宮 ( 内宮(ないくう)) です。このとき宮中には、うつしの鏡が造られて賢所にまつられているのです。
三種の神器については、古来、鏡は明照(めいしょう)・正直・智、剣は剛利(ごうり)・知恵・勇(ゆう)、玉は柔和(にゅうわ)・慈悲・仁(じん)などの徳を表わしているといわれています。神器はただ宝物として意味があるというより、こうした徳を象徴し、それを御歴代の天皇が具現されてきた伝統があるからこそ尊いと言えましょう。
私たちも、順徳天皇の示された敬神の御態度を模範として、敬神崇祖におこたりない生活をしたいものです。
「禁秘抄」は順徳天皇の撰(せん)になる宮中の故実書です。天皇は承久(じょうきゅう)の乱ののち佐渡に配流(はいる)になられたことで知られていますが、この「禁秘抄」のほか歌学書「八雲御抄」などを著され、学者、歌人としてもすぐれていらっしゃいました。
十一、天地(あめつち)の神にぞ祈る朝(あさ)なぎの
海のごとくに波たたぬ世を
我が庭の宮居(みやゐ)に祭る神々に
世の平(たひ)らぎをいのる朝々(あさなざな)
― 昭和天皇 御製 ―
「天地の」の御歌(みうた)は昭和八年の正月の宮中御歌会(きゅうちゅううたかい)始(はじめ)における「朝(あした)ノ海」の御題(ぎょだい)の御詠(ぎょえい)です。今日、多くの神社で詠舞(えいぶ)されている浦安(うらやす)の舞(まい)は、この御歌を多忠朝(おおのただとも)氏が振付けし作曲したものです。
また「我が庭に」の御歌は、昭和五十年の御歌会始めの御題「祭り」の御詠です。この御歌では特に「宮居に祭る神々」と宮中三殿(きゅうちゅうさんでん)における敬神の御叡慮(ごえいりょ)を拝察することができます。順徳天皇が「禁秘抄」に示された御敬神の御心を昭和天皇もまた受けついでおられることが、この御歌にあらわれています。
明治維新、戦前、戦後と時代は大きな変化がありました。しかし、昭和八年の御歌にも昭和五十年の御歌にも、民(たみ)やすかれ、世やすかれと祈られる大御心(おおみこころ)に変わりあろうはずがありません。この大御心は天皇陛下お一人の御心だけでなく、御歴代の大御心であり、先にも述べたように天照大神の大御心、ひいては、天地創造の大神、太一大神(お天道様)の大御心(天の理(ことわり))でもございます。
敬神生活の綱領の第三項に、「大御心をいただきてむつび和らぎ・・・・・・」とあるのも、陰陽和合を体現せる天地創造の大神・太一大神に発し、御歴代を経て今上陛下に至るまで連綿と受けついでこられたこの大御心をいただいて、私たちも日々の生活の中で、国の隆昌(りゅうしょう)と世界平和を祈り、努力をしていこうという決意をあらわしているのです。
神々が示された平和と繁栄の道を、国民が心を一つに和(わ)して、世界の人々と手をとりあいながら、追求努力してゆくことこそ神の道であり、これが私たちの踏みおこなうべき「神道」なのです。
また「我が庭に」の御歌は、昭和五十年の御歌会始めの御題「祭り」の御詠です。この御歌では特に「宮居に祭る神々」と宮中三殿(きゅうちゅうさんでん)における敬神の御叡慮(ごえいりょ)を拝察することができます。順徳天皇が「禁秘抄」に示された御敬神の御心を昭和天皇もまた受けついでおられることが、この御歌にあらわれています。
明治維新、戦前、戦後と時代は大きな変化がありました。しかし、昭和八年の御歌にも昭和五十年の御歌にも、民(たみ)やすかれ、世やすかれと祈られる大御心(おおみこころ)に変わりあろうはずがありません。この大御心は天皇陛下お一人の御心だけでなく、御歴代の大御心であり、先にも述べたように天照大神の大御心、ひいては、天地創造の大神、太一大神(お天道様)の大御心(天の理(ことわり))でもございます。
敬神生活の綱領の第三項に、「大御心をいただきてむつび和らぎ・・・・・・」とあるのも、陰陽和合を体現せる天地創造の大神・太一大神に発し、御歴代を経て今上陛下に至るまで連綿と受けついでこられたこの大御心をいただいて、私たちも日々の生活の中で、国の隆昌(りゅうしょう)と世界平和を祈り、努力をしていこうという決意をあらわしているのです。
神々が示された平和と繁栄の道を、国民が心を一つに和(わ)して、世界の人々と手をとりあいながら、追求努力してゆくことこそ神の道であり、これが私たちの踏みおこなうべき「神道」なのです。
