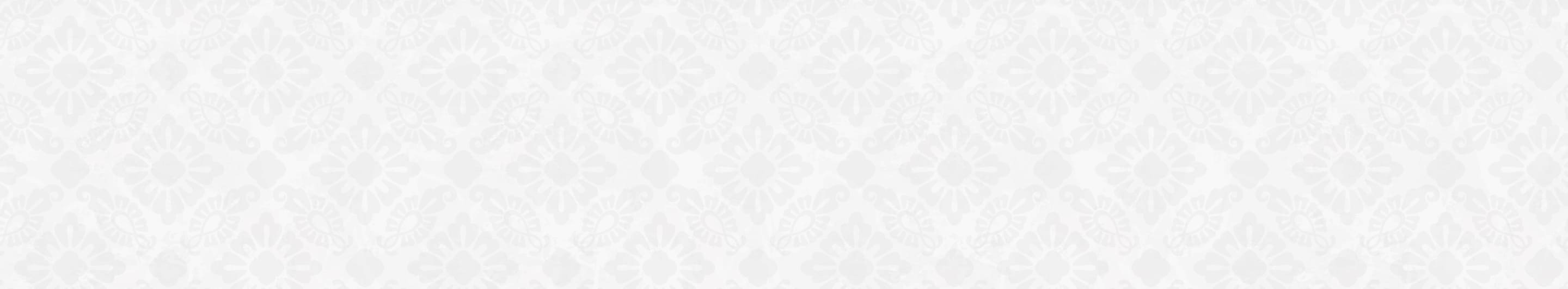
祭祀行事
春
星祭り




天社宮の星祭りは、悠久の歴史と深遠なる叡智を湛えた、誠に神聖なる儀式にて御座います。
その淵源は遥か奈良の時代に遡り、朝廷陰陽寮の泰山府君祭における「本命属星祭」として、最も重要なる祭祀行儀の一つに数えられました。この尊き儀式は、長きにわたり朝廷内にて密やかに伝承され、やがて平安の世の中期頃、「太一陰陽五行」を極めし、安倍晴明公は更なる秘儀を加え、その神聖さと深奥さを一層増したのでございます。
かくして、幾星霜を経て、朝廷陰陽寮の至高の祭祀行儀として確立され、誠に尊く、神秘に満ち溢れた祭祀となりました。
この祭祀行儀は、陰陽道の主祭神、泰山府君大神(太一)を奉斎し、紫微宮に鎮座まします星辰の神々に祈りを捧げる太一信仰の精髄を体現するものにて、他に比類なき崇高さを湛えております。
人の世に生を受けし者は、それぞれの生年月日により、太一の御分霊を宿す本命星を授かります。
本命星は、毎年、暦において、自らの定位を離れ、百八十年の星霜を経て元の座に還ります。
この神秘なる巡行の途上、性情を異にする星々との邂逅により、大小の相性・相克が生じ、心身ともに影響を受け、魂魄は遊離の状態に陥り、思いもよらぬ災厄を招来することも御座います。
かかる有様を鑑み、天の神々に祈りを捧げ、神慮を得て自らの魂魄を本心の平静に還すこと、これを帰魂と申します。災禍を遠ざけ、本命星の帰魂をより旺盛ならしめんとするのが、天社宮の星祭り「本命属星祭」の御祈祷にて御座います。
名越の祓八朔祭




水無月の「名越祓(なごし・夏越祓)」と大晦日の「大祓」は、古代中国、朝鮮などより伝来し、天の神への行儀を基として我が国で形態が整えられました。往古より朝廷陰陽寮における大変重要な大祓行儀として、平安京では鴨川の河原等に祭壇を設け「河臨祭(かりんさい)」として貴族たちの参列のもと、国家の行儀として続けられてまいりました。鎌倉幕府でもこれに習い、片瀬の浜や宇治川、琵琶湖唐崎などにおいて斎行されてきました。
名越祓には、「茅の輪くぐり」と「人形流し」という、二つの特徴ある陰陽道の儀式が御座います。これらの儀式を通じ、我々は心身の穢れを祓い、来たる季節の平安と繁栄を祈願するのでございます。
また「八朔」は八月一日を指し、実りの秋を迎える前の大切な時期にあたり、作物が無事に成長し、豊かな収穫を迎えられますよう願う農耕神事としての意味が込められております。
このように「名越祓」と「八朔祭」は、日本の人々の暮らしに深く根ざし、心身の浄化と豊穣への祈りを表す神事として、大切に受け継がれております。
【茅(ち)の輪くぐり】
境内に立てられた大きな輪をくぐる儀式にて御座います。茅の輪をくぐることにより、厄災を祓い清める御利益を授かります。
【人形流し】
人形(ひとがた)と称される、人の形を模した紙を用いる儀式にて御座います。この紙の人形は、自らの身代わりを意味し、川に流すことにより、厄を祓う力を有します。
